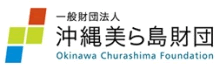身近に住んでいるクモを探して、調べて、知り尽くす 幸喜礼佳(小禄南小6年)慶悟(同小4年)・結万(同小2年)

きょうだいでクモについて調べる幸喜礼佳君、慶悟君、結万さん(写真左から)。それぞれ役割を決めて取り組んでいる=那覇市小禄の自宅
役割を分担して研究
きょうだい3人でクモについて調べるのが、幸喜礼佳君、慶悟君、結万さんだ。琉球大学にある風樹館に行ったとき、環境によってクモの種類が異なることを礼佳君が聞き、関心を持った。そして弟と妹に「一緒に調べよう」と声をかけた。
慶悟君は「最初、クモはこわいと思ったけど、毒を持っているのとそうでないものがあると分かって、あまりこわくなくなった」と印象を語る。結万さんは「クモに思い切りかまれて血が出た」とかまれたところを見せた。
3人は役割分担して研究を進めている。礼佳君は、クモの糸の強さを調べる。慶悟君は巣(す)の作り方、糸の張り方を調べる。結万さんは家の中、外、都会、水の中などさまざまな場所にどんなクモがいるのかを探す。
クモは豊見城城跡公園、末吉公園、浦添大公園、そして3人の家の前にある那覇市の小禄南風公園で採集してきた。
3人で調べているので、食卓の話題も自然と「クモ」に。「気持が一つになっている」と母の小百合さんも研究の成果を楽しみにしている。
識者コメント
外来種が在来種に影響を及ぼすと大変ですね。外来種のセイタカアワダチソウなどは他の植物が生えないように根から化学物質を出しています。アメリカハマグルマの根付近の土で他の植物が生育するか調べてみるのも面白いと思います。(與儀)