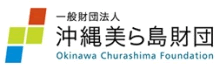沖縄県と新潟県の鳥の比較 青栁楽(知念中1年)

青栁楽君が新潟県で作った手書きの調査地図(右)と、現在調べている沖縄での地図。「尊敬する人」に鳥を描く画家を挙げるほど、スケッチは精密で美しい=南城市玉城の自宅
違いに驚き、楽しみ増大
生まれ育ったのは、豊かな自然を誇る新潟県の国立公園・妙高高原のすぐ近く。小学校3年生の頃から昨年沖縄に引っ越してくるまで公園に通い、毎朝のように公園で鳥を観察してきた。大人顔負けのバードウオッチャーだ。
ビジターセンターの探鳥会に参加し、いろいろ教えてもらううちにどんどん詳しくなり、確認した鳥は27科57種類。早朝まだ薄暗いうちから鳥の鳴き声を待ち、姿を探しては鳴き声と姿の両方から鳥の種類を覚えていった。
続けるうちに、さえずる時刻が日の出直後、明るくなってから、一日中…と種類によって異なることに気付いた。場所も、見晴らしのいいこずえや枝の中など違いがあった。さえずりは同種の仲間へのメッセージだ。さえずる場所から縄張りの大きさも想像できる。 「早い時間にさえずるのは捕食者のタカに見つからないためかも。ウグイスが一日中鳴くのは、枝の中にいて体も茶色で目立ちにくいからかな」と不思議はどんどん増え、想像力も膨らむ。
沖縄に来ると、新潟では空が明るくなる時間でも、まだ真っ暗。“レア”だったアカショウビンは自宅でも鳴き声が聞こえる。シギなど、なじみのない海鳥の種類も多い。違いに驚きながら「新潟との違いを調べたい。沖縄の鳥をたくさん見たい」と楽しんでいる。
識者コメント
昨年のサイエンスクラブで名護市屋部川周辺の鳥類調査を行った研究員がいます。頻繁にやんばるには行けないと思いますので相談に乗ってくれたらいいですね。同じ鳥のさえずりでも新潟と沖縄で比較できれば面白いです。(與儀)