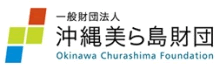カバマダラの蛹の色に関する研究Ⅱ 中嶋連誠(瀬底小6年)

カバマダラの食草であるトウワタの鉢植えを手にする中嶋連誠君=本部町瀬底
観察続け仮説立証へ
「カバマダラのさなぎにはなぜ緑とピンクの2種類があるのか」という謎の追究は2年目に突入した。昨年中嶋連誠君が立てた7つの仮説のうち、さなぎの色に関係しそうなのは(1)背景の色(2)さなぎになる時の日光の量(3)さなぎのそばに(食草の)トウワタがあるかどうか-の3つに絞られることが分かった。植物にくっついてさなぎになった場合と、人工物にくっついてさなぎになった場合でも色に違いが出ることも発見した。
「ほら、カバマダラが卵を産みに来た」と窓の外のトウワタを指差す中嶋君。トウワタの葉を見せながら「これは今日産み付けられた卵で、こっちは2回脱皮した幼虫」と楽しそうに教えてくれる。今年は台風の影響なのか幼虫が少なく「幼虫待ち」の状況が続くが、「人工物での蛹化で緑になる条件と、植物での蛹化でピンクになる条件が探れれば、色の変化の要因が分かるはず」だと考えている。
一言アドバイス
さなぎが2つの色になる条件を、いろいろ仮説を立てて研究しているのは、とてもよいと思います。しっかりと考えて研究してきましたので、これからも思うように進めましょう。(西平)