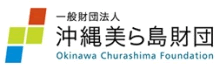汚染された河川のpH調整による水質改善~pH改善による微生物の変化~
沖縄市立美東中サイエンス部化学班 岩下光太郎、島袋優真(以上2年)、高良悠生弥(3年)
水質測定を基に県がA~Eにランク付けした河川を本島から6カ所選定し、それぞれ上中下流のpHを測定。汚染が進む河川の水を酸性の四つの試薬で中和させ、水質改善を試みる。併せて水中の微生物も観察し、中和反応後の影響も調べる。
研究を進めるにあたり「きれいな水」の定義づけが課題という。また、とった水の中に微生物が少ないことから、採水方法も改めて検討することにしている。
岩下光太郎さん(13)は「実際に河川に試薬を流せないが、この研究が環境保護に役立てられるようにしたい」と意気込み、島袋優真さん(14)は「海同様に河川も誇れる沖縄にしたいので、楽しく研究している」と意義を強調する。中学生活最後の研究となる高良悠生弥さん(14)は「経験や知識を生かして、二人を支援したい」と話した。
水質改善の方法として、水槽の中できれいな川の微生物を石に住み着かせ微生物を石ごと川に入れて有機物を分解させる方法や、水際に生えている植物で浄化する方法があります。沖縄産の抽水植物を見つけて利用してはどうでしょう。 (與儀)
「きれいな水」へ意欲

試薬を使って水を中和し、県内河川の環境改善に向けた可能性を探る美東中サイエンス部化学班の(左から)島袋優真さん、高良悠生弥さん、岩下光太郎さん=2019年8月、沖縄市高原
水質測定を基に県がA~Eにランク付けした河川を本島から6カ所選定し、それぞれ上中下流のpHを測定。汚染が進む河川の水を酸性の四つの試薬で中和させ、水質改善を試みる。併せて水中の微生物も観察し、中和反応後の影響も調べる。
研究を進めるにあたり「きれいな水」の定義づけが課題という。また、とった水の中に微生物が少ないことから、採水方法も改めて検討することにしている。
岩下光太郎さん(13)は「実際に河川に試薬を流せないが、この研究が環境保護に役立てられるようにしたい」と意気込み、島袋優真さん(14)は「海同様に河川も誇れる沖縄にしたいので、楽しく研究している」と意義を強調する。中学生活最後の研究となる高良悠生弥さん(14)は「経験や知識を生かして、二人を支援したい」と話した。
〈一言アドバイス〉
水質改善の方法として、水槽の中できれいな川の微生物を石に住み着かせ微生物を石ごと川に入れて有機物を分解させる方法や、水際に生えている植物で浄化する方法があります。沖縄産の抽水植物を見つけて利用してはどうでしょう。 (與儀)